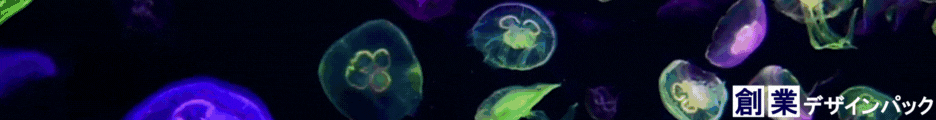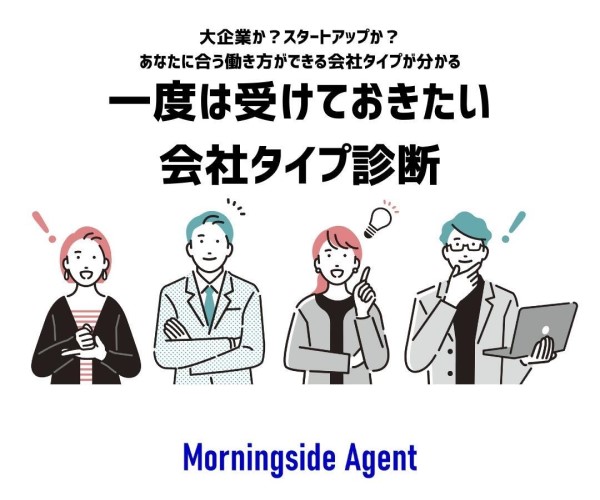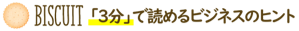時代は令和になり、新型コロナ流行の影響もあって、顧客の購買行動が増々多様化していく現代。
そんな時代において、顧客と向き合い、上手く成果につなげていくのは、なかなか難しいものです。
ここでは、マーケターなら絶対に知っておくべき「カスタマージャーニーマップ」について、その概要や作成の目的、具体的な作り方の手順について紹介します。

カスタマージャーニーマップとは
カスタマージャーニーマップとは、あらゆる商品やサービスを消費者が認知し、実際に購入、使用するまでの行動、思考、感情の遷移(カスタマージャーニー)を時系列に沿って可視化したもの(マップ)です。
「ジャーニー(Journey)とは、「旅」を意味します。
ITの発展によりSNSをはじめとするインターネットが広く普及し、多くの消費者がオンラインショップなどを利用するようになりました。
それにより、以前よりも購買パターンが複雑化し、顧客の選択肢も増えたということがあります。
そのような状況に対応し、効率的かつ効果的なマーケティング戦略を立てるための施策の一つとして、カスタマージャーニーマップが注目を集めています。
カスタマージャーニーマップの作り方
それでは、カスタマージャーニーマップの作り方について、概要をご説明しましょう。
ステップ1:目標やペルソナを設定する
まず、マップを作成する目標や、ペルソナの設定をします。
消費者の購買行動を把握し、共有するため、という一般的な目的に加え、新商品の販売や新規顧客の獲得、ターゲットの拡大など、企業独自のゴールも立てるのが望ましいでしょう。
その後、ターゲットの年齢や職業、性別、課題などを明確にし、ペルソナを決めていきます。
【参考】ペルソナ分析とは?現代のマーケターには必要不可欠のスキル
ステップ2:「縦軸」の項目を精査する
マップ作成の目標及びペルソナが設定できたら、カスタマージャーニーマップの大きな枠組みとなる、「縦軸」の項目を精査、設定します。
縦軸には主に消費者が実際に商品やサービスを購入、利用するまでの「行動」「思考」「感情」そして「課題」これらの4つの要素を含めます。
必要に応じて、消費者がどんな手段で情報を仕入れるのか、もしくはどこで購入するのか、具体的な「タッチポイント」や、自社の「アプローチ方法」などを加えるとより綿密なマップに仕上がります。
ステップ3:「横軸」にフェーズを設定する
次に、横軸の項目を設定していきます。
基本的には、「認知」→「興味・関心」→「情報収集→比較検討」→「購入」→「評価」の5段階のフェーズになりますが、必要に応じて評価の後に「拡散」「呼び込み」等の項目も付け加えます。
ステップ4:実際にフレームワークを埋めていく
「縦軸」「横軸」の項目を設定し、枠組みができたら、その中身を実際に埋めていきます。
その際に、顧客の感情や思考については文字だけではなく、一目でわかるような記号や顔文字を使うことでより可視化しやすくなります。
一度全てが埋まったら、実際の商品開発プロジェクトやマーケティング施策との整合性をはかり、何度も見直し、修繕を加えてより完璧なものに近づけていきます。
カスタマージャーニーマップ作成のメリット
それでは、商品やサービスの提供者側にとっての、カスタマージャーニーマップ作成のメリットについて見ていきましょう。
①複雑化した顧客の購買行動に対応できる
カスタマージャーニーマップ作成の最大のメリットは、PCやスマホ、インターネットやSNSなどの普及により複雑化、肥大化した消費者の行動パターンや情報選択に対応したマーケティングを実現できることです。
大雑把な顧客イメージや消費者の行動パターンを想定する従来のやり方は見直されつつあり、近年では消費者一人一人に焦点を当てる「One to Oneマーケティング」が重要視されています。
消費者の視点に立ち、需要のある商品やサービスの開発、提供するための施策としてカスタマージャーニーマップの作成は非常に効果的なのです。
②サービスにおける一貫性の追求につながる
カスタマージャーニーマップをあらかじめ作成し、それに沿った販促施策が実現できれば、商品のコンセプトやサービスにおける「一貫性」の追求にもつながります。
世界中にチェーン店を展開するスターバックスを例に挙げると、どの国の、どの店舗に行っても、基本的に顧客は同じ水準の品質のサービス、商品を享受できます。
一貫性を追求することは、企業ブランドの向上、信頼獲得をするためにも決して欠かせません。
③企業内における認識の「ズレ」を防止できる
また、商品開発から販売にまで携わる全ての担当者、社員など、企業内における認識のズレを防止できます。
提供する商品やサービスのコンセプトやターゲット、提供手段など予め可視化し共有すれば、意思決定も迅速になります。
ブランディングという側面に留まらず、業務の効率化にもつながるでしょう。
まとめ
以上で紹介したマップの作り方は、あくまでも一例に過ぎません。
業種や業態によって作る目的やマップの概要、必要な項目は異なるため、これが正解というものはないと考えてよいでしょう。
また、一度マップを作成し終了ではなく、チームや担当部署で共有し、適宜改善、修正を加えていくことも必要になります。
実際のペルソナの行動や感情の変化にどれだけ即したマップが作れるか、どれだけわかりやすく作れるかという点を重視して作成していきましょう。