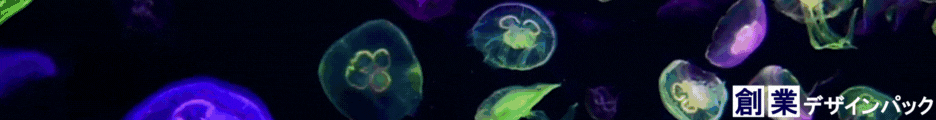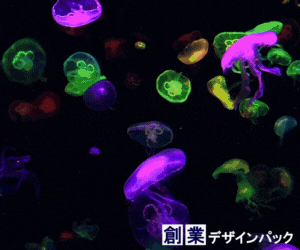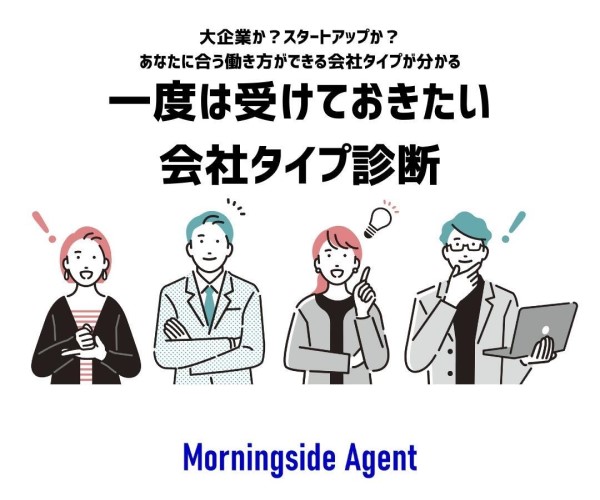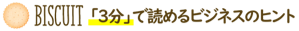働き方や、人材の多様化の波が押し寄せる、今の世の中。
これまで通りの手法に固執していては、顧客も人もひきつけられません。
そんな世の中のニーズに応えるため、そして新しい時代で生き残るために、企業はその組織在り方をも問われるようになりました。
今回は、徐々に注目を集めつつあるホラクラシー組織について、その特徴や可能性について解説します。
【参考】ジュニアボード制度とは?若手の力を成長に繋げる仕組を解説

ホラクラシー組織とは?
ホラクラシー組織とは、社内に役職や階級といった概念が存在せず、社員の誰もがフラットな関係を築いている組織を意味します。
年齢や職歴による上下関係が存在しない、というのは、心配する人もいるかもしれません。
しかし、誰もが対等な立場で意見やアイディアを出しながら働ける、まさに理想的な環境とも言えるでしょう。
ホラクラシー型組織はどのように運営されるか
組織内では意思決定権が個人、もしくはチーム単位に分散されます。
そのため、各個人が大きな裁量を持ち主体的に事業に取り組むことが期待されています。
元々は、2007年ごろからアメリカで広まった概念。
日本では、
などが導入しています。
ヒエラルキー組織との違い
ホラクラシー組織と対になる概念として、ヒエラルキー組織が挙げられます。
- 働き方
- 意思決定権
- 情報共有
という3点に関し、ホラクラシー型組織とヒエラルキー型組織、両者の違いを見ていきます。
ヒエラルキー組織
ヒエラルキー組織とは、ピラミッド型の階層がある組織。
役職によって、社員間で上下関係が発生するのが大きな特徴となります。
国内にある大半の企業は、このヒエラルキー組織に該当するでしょう。
基本的に、上の命令は絶対。
社員は企業理念を尊重した上で、上司からの指示、命令の元で働くことになります。
意思決定権も管理職や部長、社長、取締役などの、位の高い役職に帰属します。
そのため、部下は、基本的に何をするにも醸造部の承認や許可が必要となります。
情報共有に関しては、ヒエラルキー組織の場合、機密性の高い情報程上層部に集中します。
ホラクラシー組織
ホラクラシー組織でも、もちろん、企業全体としてのルールや理念は存在します。
しかし、その枠の中で、社員は比較的自由に行動できるのが特徴。
また、意思決定権については、特定の役職や人物に限定されるというわけではありません。
各チームや個人単位で分配されるため、権力が一点に集中することは基本的にないのです。
情報共有に関しても企業に関わることなら、基本的に社内の隅々まで拡散されます。
【参考】役職定年制とは?役職任期制との違いやメリット・デメリット
ホラクラシー組織の可能性と注意点
それでは、まず、ホラクラシー組織の可能性について見ていきましょう。
自主性や主体性の強化が見込める
まず、意思決定権が個人レベルで分配され、社員一人一人の裁量が大きいことから、自主性や主体性が強化されることが見込めます。
周囲の目や空気を気にせず、自分の意見を主張したり、型にはまることなく働けます。
そのため、独創的で斬新なアイディアも生まれやすくなるでしょう。
意思決定のスピードが速まるためムダを削減しやすい
次に、上司の承認や許可を得る等の手続きが大幅に減ることから、業務の生産性や効率アップも期待できます。
その結果、意思決定や仕事そのもののスピードが速くなるでしょう。
また、プロセスのムダの削減にもつながると言えます。
それでは、注意点について見ていきましょう。
責任の所在が曖昧になりがちで失敗時リスクが高まる
まず、統率が取れなくなったり、責任の所在が曖昧になったりする可能性があります。
いくら自由度が高いとはいえ、仕事には必ず責任が伴うもの。
誰もが好きなように動いていたらまとまるものもまとまらない、ということもあります。
その結果、社員同士が失敗の責任の擦り付け合いをして雰囲気が悪くなるといったリスクも。
そうすると、事業の成功率が下がってしまうことにもなりかねません。
社員に自主性がないとそもそも成り立たない
また、ホラクラシー型組織は、社員一人一人に確固たる意思や仕事に対する熱意、主体性がないとそもそも成り立ちません。
一部の社員だけが怠け、一部の社員だけが働くという状況に陥ると、本末転倒。
他力本願な社員が少しいるだけで、全体が乱れてしまうのです。
ホラクラシーに関する教育に時間がかかる
国内でも、一部の企業はすでにホラクシー組織制度を導入しています。
しかし、まだ十分に認知されていない上、日本企業に馴染ませるには時間もかかりそう。
そのため、まずはホラクラシーとは何か、という教育から始める必要があります。
ホラクラシー型組織の意義や、実施目的を社員に理解してもらう必要があるのです。
知識が曖昧のまま、無理矢理導入を進めようとしても、混乱を招くだけかもしれません。
多くの時間と手間を費やし、理解を深めていく必要があるでしょう。
【参考】ボトムアップ経営とトップダウン経営の違いや特徴を徹底比較
まとめ
元々ヒエラルキー組織で運営されてきた企業が、いきなりホラクラシー制を導入することは現実的に難しいところもあるかもしれません。
無理に導入しようとすると大きな混乱が発生する可能性もあります。
まずは一部の部署や、チーム、子会社など、小規模単位で進めていくのが徐々にその規模を大きくしていけるよう心がけましょう。