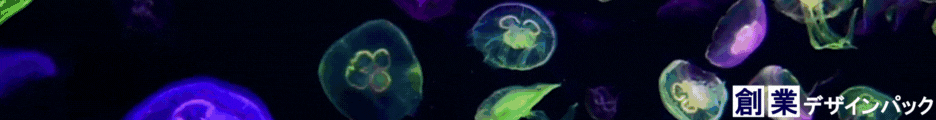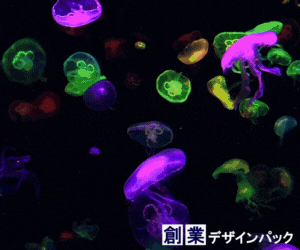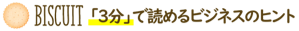今や深刻な社会問題の一つとなりつつある、パワーハラスメント、通称「パワハラ」。
これは、どんな組織でも起こり得る、決して無視できない問題です。
2022年4月から、中小企業も対象となるパワハラ防止法が施行されます。
ここでは、パワハラ防止法の概要や、パワハラの定義を踏まえた上で、企業が講じるべき具体的な対策を紹介していきます。
【参考】ノー残業デー上手くいってる?形骸化させないためのコツ5選

パワハラ防止法とは?
業種、業態、企業規模、民間、行政を問わず、多くの企業で横行する、パワハラ。
時には、従業員や組織の構成員を、休職や離職にまで追い込んでしまうことがあります。
そこで、パワハラの発生を防ぐため、政府は2020年6月から、改正労働法施策総合推進法、通称、パワハラ防止法を大企業を対象に施行しました。
これは、2022年4月から、中小企業もその対象に加わることになります。
パワハラ防止法の施行に伴い、対象となる企業はパワハラ防止のための対策を講じることが義務付けられます。
実は、それに応じなかったり、対策が不十分だったりした場合の罰則等は特にありません。
しかし、企業名の公表や勧告など、行政指導の対象とはなり得ます。
その結果、企業のイメージを損なうリスクが生じ得るでしょう。
職場におけるパワハラの定義
防止策を講じる前に、まずどんな行為がパワハラに該当するのか押さえておきましょう。
職場におけるパワハラとは、
- 優越的な関係を背景とした言動で
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもので
- 労働者の就業環境が害されること
と定義されます。
パワハラは上司から部下に対して行われるものと認識されがち。
しかし、上記の1.の基準により、実は部下から上司に対するパワハラも存在します。
【参考】安全配慮義務とは?心の健康も含む?罰則は?対策5つを紹介
企業に求められるパワハラ対策
それでは、パワハラ防止法の施行に伴い、対象となる企業が講じるべきパワハラ対策のための主な取り組みを紹介します。
1、パワハラに対する企業方針の明確化と周知
事業者はまず、企業におけるパワハラの方針を決める必要があります。
更に、それを従業員に周知する必要があります。
そして、前段の、”3つ要件”を踏まえた上で、
- 具体的にどんな言動がパワハラに該当するのか、リストを作成する
- パワハラに対する企業のスタンスを表明する
といったことにより、対策のための準備を進めていきます。
また、パワハラを行った者への処罰の内容も制定しましょう。
就業規則に記載することも忘れてはいけません。
2、相談、通報窓口の設置や初動の対応策を決める
万全な対策を講じたとしても、パワハラの発生を100%防ぐことは現実的に難しいかもしれません。
万一の事態を想定した上での対応策も必要となります。
例えば、
- 被害に遭った人がすぐに誰かに助けを求められるよう、相談窓口や通報窓口を設置する
- 誰が、どんな対応を取るのか具体的な初動の内容を決める
といったことをしておきます。
相談、通報のための窓口は、ただ設置するだけでは認知してもらえないケースもあります。
場所や利用方法について、従業員に周知しましょう。
3、パワハラ問題関係者のプライバシーの保護
パワハラに限ったことではなく、社内で何かの問題が発生した際、被害を訴えたり、通報したりすると二次的な被害(セカンドハラスメント)に遭うことがよくあります。
そのため、セカンドハラスメントが発生しないような心配りも必要になります。
相談者や通報者のプライバシーを守るための取り組みも並行して行わなければなりません。
ハラスメントに関する相談があった場合には、
- 適切な措置を取ること
- 関係者のプライバシーを守ること
- 相談、通報された内容を元に不当な取り扱いをしない、させないこと
これらは、事業者が守るべき義務です。
4、早期解決を図るためのプランの策定
ハラスメント関連の問題が起きた場合、収束までには、通常多くの時間を要します。
裁判沙汰に発展するとさらに長期化することがあるでしょう。
時間が掛かればそれだけ、トラブルが外部に漏れるリスクも高まり、企業イメージや社会的信用にも影響しやすくなります。
なるべく早く、問題の解決を図るための具体的なプランも、専門家らの意見を聞きながら練っていきましょう。
【参考】ホワイト企業とは?認定されるための7つの指標と取り組み
パワハラ防止法に対応できるようにしよう
パワハラ防止に向けた取り組みは、従業員が安心して働くために重要なこと。
もちろん、企業イメージや組織の安定にも関わることです。
問題が日常的に起きていたり、その状態を事業主が放置していたりすると、人材の流出や社会的信用を失うことにもなりかねません。
パワハラを含め、ハラスメント関連の問題は、複雑化しやすいという特徴があります。
また、可視化されないことも少なくありません。
そのため、対策を練ろうと思っても一筋縄では行かないケースもあります。
事業主や責任者らが一方的に対策を練るのではなく、従業員との意思疎通を図り、現場の意見を取り入れながら有意義な対策を講じていきましょう。