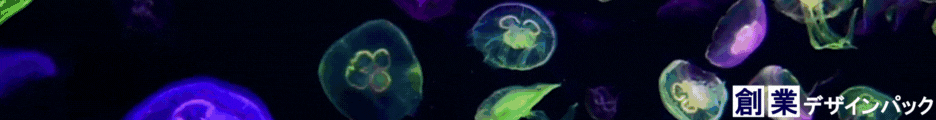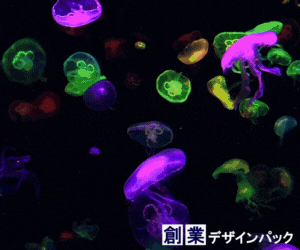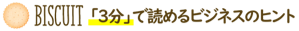新規事業の立ち上げのため、そして安定した経営や雇用の獲得のため。
助成金や補助金は個人事業主にとってたいへん重要な公的制度です。
しかし、それぞれに、受給のための条件や審査があります。
誰もが簡単に利用できるというわけではありません。
必要な制度を必要な時に活用するためにも、事業者が利用できる助成金、補助金制度についての理解を深めましょう。
【参考】個人事業主が加入できる社会保険は?老後やピンチに備えよう

助成金と補助金の違い
助成金、補助金とも基本的に返済義務の無い事業者向けの経済支援制度です。
しかし、目的、管轄、制度を利用するための要件に関して、それぞれ違いがあります。
助成金
助成金とは、主に雇用や需要の拡大、起業の促進など、国の政策実現を目的とした制度で、主に厚生労働省が管轄しています。
助成金の対象には個人事業主や民間団体、一般企業が含まれ、受給の要件を満たし審査に通れば比較的容易に利用できます。
助成金は後払いが基本で、実際に会社を設立したり事業を始めた後に事後申請します。
補助金
補助金とは、経済の活性化などの国策を実現させるために交付されるお金で、基本的に経済産業省が管轄しています。
都心から離れた地域の活性化を目的とした補助金もあり、その場合管轄は地方公共団体や商工会議所になります。
補助金は助成金とは異なり、全体の予算があらかじめ決められていることから受給のための申請期限や審査が比較的厳しく、要件を満たしていても利用できないケースも珍しくありません。
【参考】【2022年版】働き方改革導入で貰える助成金・補助金5選
個人事業主が利用できる助成金4選
個人事業主が従業員を雇う場合などに活用できる助成金は以下の4つになります。
いずれの制度も厚生労働省が担当しています。
①地域雇用開発助成金
特に地方出身者であれば「田舎は仕事がない」という言葉をしばしば耳にするのではないでしょうか。
あくまで一般論ですが、事業者は、インフラが整っていて、人も顧客もチャンスも多い都市部に出ていこうとするもの。
そして事業者が都市部に出て行ってしまうと、田舎は仕事がなくなり、若者は都市部に出ていき、地方の過疎化が進んでしまいます。
しかし、「別にそれはそれでいいんじゃない?」とはいきません。
そこで、雇用機会が特に不足している地域において事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇う場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成しようとするものです。
雇用にかかる経費や事務所の設置、整備にかかる経費が主に助成の対象となり、従業員の増加に伴い給付される金額も増えます。
地方で事業をしている方や、地方に出ていこうと考えている方は、チェックする価値があるかもしれません。
②人材開発支援助成金
ご存知の通り、世の中は益々複雑になり、求められる仕事のレベルも上がってきています。
多くの人が、パソコンをはじめ、様々なツールを使って仕事をすることを求められます。
「仕事はあるし、人間はいる。でも、出来る人がいない。訓練する?制度を導入する?無理無理、そんな余力ない!」
そんな課題に対して、国がサポートしますよ、という助成金です。
この制度は、
- 従業員の訓練に関連するもの
- 事業者の制度導入に関するもの
の2種類がありあす。
訓練に関するもの
訓練関連のものは、事業者が雇う雇用保険の被保険者である従業員が、その事業に必要な専門的知識やスキルの習得のために要した訓練費用を助成します。
訓練には、労働の生産性を向上させるための「特定訓練コース」と、それ以外の「一般関連コース」があります。
制度導入に関するもの
制度導入に関するものは、事業者が人材育成やキャリア形成に取り組むための制度を導入した際、その経費が助成対象となります。
③トライアル雇用助成金
世の中には、何らかの事情で職歴がなかったり、長いブランクがあったり、これまで安定した職歴を持たない人が存在します。
そして多くの場合、企業はそのようなタイプの人を雇うのを避ける傾向にあるもの。
しかし、実際雇ってみたら、実は能力が高いかもしれないし、これまでは運が悪くマッチした会社に巡り合わなかっただけかもしれず、次はマッチするかもしれないし、やむを得ない事情でブランクを抱えているだけかもしれないし、以前は不真面目だったとしても、何かきっかけがあって変わったかもしれません。
そのような、一般的には避けられがちだけれども、働く意欲がある人を、「ちょっとトライアルで雇ってやってよ」と、雇用するよう事業者に促す制度です。
例えば、就労経験がない、持病があると言ったなんらかの事情によって長期的に安定した職につくことが困難な者を従業員として雇い入れた際に支給されます。
原則として該当する従業員一人に対し月額4万円、最大3ヶ月分を一度に受給します。
④特定求職者雇用開発助成金
意味合いとしては、「③トライアル雇用助成金」に近いかもしれません。
高齢者や障がいのある者などを雇い入れる際に事業者に対して給付されます。
諸事情により長時間の勤務が難しいが、経理や秘書、事務などの短時間勤務ならできる、という労働意欲のある方を採用し、即戦力として開発することを目的としています。
最大3年間で240万円の助成となっており、従業員の年齢や障がい等級によって支給額や期間が異なります。
【参考】個人事業主の老後資金対策!加入できる年金制度をざっくり!
個人事業主が利用できる補助金2選
新規事業を始めたいけど資金が足りないと言った場合に以下の補助金制度を利用することで資金調達がスムーズにできます。
①創業補助金
新規事業を始める事業主にとって最もポピュラーな補助金です。
新たな需要や雇用の創出、経済の活性化を目的としています。
創業するにあたって資金が出るとなると、一歩踏み出そうとしている人にとっては、大きな支えになります。
一人以上の従業員の採用を予定している事業者や企業が対象です。
新規事業の立ち上げのために必要な経費全般が最大200万円まで補助されます。
申請期間は年度ごとによって異なるため、中小企業庁のホームページや自治体の担当窓口でチェックしたり、相談会に参加した上で申請しましょう。
毎年多くの申請があり、事業計画書の作成など必要書類が多く審査自体も厳しめであることから、希望する際には入念な準備が必要です。
②小規模事業者持続化補助金
卸売業、小売業、サービス業、製造業など、比較的小規模な事業者を対象とした補助金制度です。
最大50万円の現金給付に加え、経営や事業拡大に関する指導も受けることができるます。
新米の事業者は、積極的に申請しましょう。
申請期間や申請方法に関しては、主催している日本商工会議所のホームページに詳しく記載されています。
【参考】税金対策してない?知らないと損する個人事業向けの対策9つ
まとめ
助成金や補助金には以上で紹介した制度に加え、社会情勢や経済状況に応じて新たに導入されるものも多数あります。
個人事業主としてビジネスに携わる以上、受けられるサポートや制度に関する情報を集め、事業の安定を維持する努力は必要不可欠。
上限があるもの、審査が厳しいものもありますが、積極的に助成金や補助金を活用していきましょう。