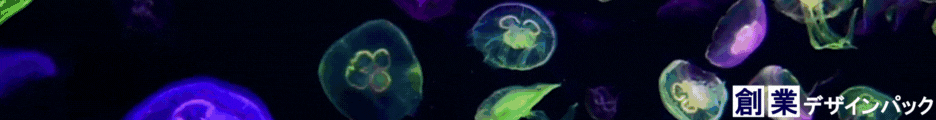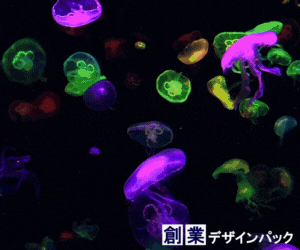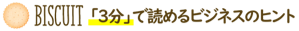法律によって手厚い保護を受けられるサラリーマン。
それに比べると、フリーランスは「自分の身は自分で守る」的な側面があります。
人手も知識もお金もない中、企業と対峙していくのは並大抵のことではありません。
しかし、守ってくれる法律がないわけではありません。
特に下請法については、必ず知っておくべきとも言えます。
ここでは、フリーランスなら最低限知っておくべき、下請法の知識について解説します。
【参考】源泉徴収とは?フリーランスや副業者のために基本から丁寧に

下請法とは?
下請法の正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」です。
仕事を発注する側、受注する側との間の公平な取引を実現し、下請け側、つまり、フリーランスの利益を保護するために作られた法律です。
独占禁止法の特別法にあたり、資本金1000万円以上の法人クライアントと取引する際に適用されます。
- ウェブコンテンツなどの「情報成果物の制作」
- 運送
- 印刷
- 弁護士、税理士などの専門的知識
- 技能等に基づく「役務の提供」
- その他「物品の製造・修理」
などの委託業務が対象となります。
【参考】副業者、フリーランス必見!青色申告と白色申告の違いまとめ
下請法で定められている義務とよくある違反行為
それでは、フリーランスとして最低限知っておくべき下請法の内容と、よくある違反行為についてを見ていきましょう。
書面の交付義務
まず、クライアントはフリーランスと契約を結ぶ必要があります。
そして、実際に仕事を依頼する際には、契約書や発注書など、書面を交付することが義務付けられています。
書面には、
- 具体的な仕事の内容
- 報酬額
- 納期
- 品質に関する基準
- 支払期日
- 支払方法
- その他重要な取り決め
について記載する必要があります。
単なる口約束で仕事を進めようとしたり、内容に不備のある書面をもって契約を結んだりしてしまうと、後から必ず問題がおきます。
たとえば、
- 納品後に報酬を減額されてしまった
- 急に仕様変更されてしまった
- 発注そのものを取り消されてしまった
など、受注側が大きな不利益を被る事態に陥ってしまうでしょう。
報酬の支払い期日を定める義務
下請法には書面の交付義務とは別の項目として、報酬の支払い期日を定める義務も含まれています。
クライアント企業は、成果物を受領してから原則として60日以内に、できる限り早い期日に報酬を支払わなければなりません。
遅れた場合には、遅延利息として年率14.6%を乗じて支払う必要があります。
フリーランスにとって、報酬の支払遅延や未払いは、仕事や生活にも大きな影響が出るもの。
契約を結ぶ段階で、必ずクリアにしておきましょう。
クライアントが成果物を受け取る義務
フリーランスとして働いていると、成果物を納品しようとしてもクライアントが受け取ってくれなかったり、もしくは返品を要求されたりする事態に陥ることがあります。
特別な理由がない限り、成果物の受け取りを拒否したり、返品したりすることは下請法で認められていません。
発注側は、発注したものは原則として受け取らなければならないのです。
取引記録の保存義務
下請法では、納品後のトラブルを回避するために、
- 納品した成果物
- それに関する発注書
など、取引記録がわかるものを2年間保存しておく義務が発注側に課されます。
【参考】個人事業主なら提出すべき開業届の基礎知識と2つのメリット
下請法が適用されない場合は?
ちなみに、資本金1000万円未満の企業との取引は下請法の適用外となります。
しかし、かといって、フリーランスが保護されないわけではありません。
その場合は、独占禁止法で保護される可能性があります。
「違反行為をされた」と思ったら、まずは、クライアントに異議を申し立てましょう。
それでも解決が見込めない場合には、フリーランス110番、もしくは弁護士を頼りましょう。
フリーランスの味方、フリーランス110番とは?
フリーランス110番とは、第二東京弁護士会が、内閣官房、公正取引委員会、厚生労働省、中小企業庁と連携しながら運営するホットラインです。
個人事業主など、労働基準法の労働者と見なされない方なら誰でも無料で利用可能。
下請法の違反も含め、
- 「あいまいな契約のまま一方的に仕事を押し付けられた」
- 「ハラスメントの被害を受けた」
- 「報酬を支払ってもらえない」
などあらゆる問題を、フリーランスに関する法律問題に詳しい弁護士が対応してくれます。
下請法、独占禁止法等の違反行為が認められず、フリーランス、クライアント間での問題解決が見込めない場合には、和解のあっせん手続きもしてもらえます。
何かトラブルが生じた際にはぜひ利用してみましょう。
【参考】副業から起業へ!段階を踏んだ起業のメリット3つと注意点3つ
まとめ
フリーランス業において、クライアントとの健全な取引を実施するためには、最初に契約内容をクリアにしておくことが一番です。
しかし、お互いの知識不足によって意図せず違反行為が発生してしまうケースもあるでしょう。
そして、中には故意に欺こうとしてくる悪質な企業もあります。
そのため、泣き寝入りしないためにも、下請法についてある程度の知識を身につけておきましょう。
些細なことでも取引上何か問題が発生した際には、第三者の助けを求めましょう。